こんにちは~モリオカです。2人の子供の成長記録も兼ねて、日々の出来事や便利だったもの、子育てに関する情報などを当ブログで発信しています。
長女(小3):国語は嫌いだけど漢字は好き
次女(年長):こどもちゃれんじを受講中
新学期に「担任が新任の先生」と聞いたとき、不安に感じていませんか?特に小学校や中学校では、子どもの学校生活に直結するだけに、保護者としては心配になりますよね。実際、私も新学期に「新任の先生」と聞いて戸惑いましたが、1年を通して見えてきたのは“新任だからこそ得られる学び”や“サポートの大切さ”でした。
この記事では、新任の担任に対する不安の理由と、子どもがしっかり成長していく過程を実体験からお伝えします。親としてどんな姿勢で関わればよいのか、具体的なポイントもご紹介します。
担任が新任の先生に…小2の春、親として感じた最初の異変とは?
振り返ってみると1年生とは違った面で2年生もなかなか大変でした。小学校2年生に進級した春。長女はすでに学校や学童に慣れており、親としても安心していました。しかし、担任が大学卒業したての新任の先生だったのです。1年生のころは学年主任のベテランの先生が担任だったので、授業も生活指導も安心感がありましたが、今回は全くの新人。とはいえ、最初は何とかなるだろうと楽観視していました。
ところが、4月早々に異変が起きたのです。授業の内容や進め方が、ベテランの先生とはあまりにもギャップがありすぎたのでしょう。娘の口から、学級崩壊ともとれるエピソードも含めいろいろ不満や問題を聞いているのでいくつか紹介したいと思います。

4月早々、「授業が分からない」と言い出す
長女が2年生になり、4月早々に「ちえが分からない」としきりに言い出すようになりました。国語の授業で「たんぽぽのちえ」という教材を扱っていたようですが、最初は「知恵」という言葉の意味が分からないと思い、丁寧に説明してみました。
しかし、娘は一向に納得せず、数日後にも「ちえ」が分からないと繰り返します。ついには、学校の相談室に自ら足を運んで相談しに行ったようでした。この時点で、ようやく私たち親は「ちえ=知恵」の意味が分からないのではなく、授業の内容自体が理解できていないのだと気づいたのです。
子どもは語彙が少なく困っていることを大人のようにうまく言葉で表現できません。大人がしっかりと子どもの話に耳を傾け、真意をくみ取ることが大切だと痛感しました。

そんなに授業が分かりずらいんだね
授業参観で明らかになった「時間配分の甘さ」
4月末に授業参観が行われましたが、先生の授業の進行に少し不安を感じました。授業のテーマは、「遊園地での迷子のアナウンス」。黄色い帽子をかぶってる、どんな服装をしているかなど、迷子の様子をどのように伝えるかを班ごとに考え、最後に各班発表するという内容でした。
先生:「さあ、どんなアナウンスをすれば迷子の特徴を伝えられるかな。」
先生:「班ごとに考えてみましょう!」
児童: ワイワイ、ガヤガヤ
先生: 各班を巡回して、話し合いの様子を見て回る
児童: ワイワイ、ガヤガヤ
先生:「終わった班はあるかな??」
児童:「まだー」
児童: ワイワイ、ガヤガヤ
(気づけば、チャイムがなる)
先生: 焦った様子で、「じゃあ、3班発表おねがい!」
授業終了の鐘がなった後で、1つの班だけ発表させて授業は終了。娘のクラスだけ10分以上時間をオーバーするとという事態に見舞われました。去年のベテランの先生とのギャップを身をもって感じた授業参観でした。

時間配分がいまいちでした。
男子児童の騒がしさと授業の中断
長女によると、授業中に男子児童が頻繁に席を立ったり騒いだりして、授業が何度も中断されるとのこと。先生はその都度対応に追われ、他の児童へのフォローが手薄になっていたようです。
たとえば、隣の子とペアを組んで問題を出し合う場面でも、相手が席を立った男子児童だとペアを作れず、一人で待つしかないことも。ベテランの先生のときには見られなかった混乱が、授業中に頻発していたようです。

頻繁に席を立つ子がいて、授業がそのたびに止まるそうです。
なぜか誕生日のお祝いが2月から始まる
後半になって、余裕ができたのでしょうか。娘の話ではなぜか、2月から朝の会でお誕生日の子のお祝いがあったそうです。 「え??ていうか、なぜ途中から始めたの???」誕生日が早い子は祝ってもらえないのでは…….と疑問に感じました。幸い娘は3月生まれなので良かったですが。少し余裕が出来たのだと思いますが、ややちぐはぐな印象を受けました。
「1年1組は、ダメ!!!」と妹にアドバイス
ある日、次女が「小学校ではやさしい担任の先生がいいな」と話していたところ、長女が「1組はダメ!2組じゃないと授業が分からない」と発言。新任の先生=1組、ベテランの先生=2組という印象がすっかり刷り込まれていたようです。
娘の小学校では2組=学年主任ですが、毎年の担任は異なるため「1組=新任」とは限りません。自分の経験をもとにして、妹に良かれと思ってアドバイスしたのでしょうが、妹も混乱してしまうので「変なことを吹き込まないで…」と内心ヒヤリとさせられました。

よほど授業が分からなかったのでしょう。
少しずつ見えてきた新任の強みと子どもの変化
さて、ここまで愚痴ばかり書いてしまいましたが、新人の先生と言えども良いところはたくさんあります。“新任だからこそできる児童との関わり方”が、少なからず子どもたちに良い影響を与えている部分も感じました。

若さは魅力の一つです。新任の先生から学べることも多いのでは???
一緒に遊んでくれる若さと体力
休み時間に鬼ごっこをしたり、体育の授業でも一緒に走ったりして、子どもたちと体を動かして関わる姿勢に娘はとても喜んでいました。「先生が一緒に遊んでくれるのが楽しい!」とのこと。これは若い先生ならではの魅力です。
情報機器を活用した授業
娘によれば、授業ではタブレットの写真や資料をプロジェクターで黒板に投影するなど、タブレットをうまく活用しているとのこと。後述する3学期授業参観でも、視覚的に理解しやすい工夫が感じられました。年配の先生よりもデジタル機器の扱いに慣れている新任の先生ならではの強みだと思います。
子供の自立のきっかけになるかも
新任の先生は、どうしても細かいところへの配慮が足りないこともあります。しかし、それが子ども自身が考え、行動する“自立”のきっかけになることもあると感じました。娘が相談室を自ら訪れたのはその一例です。幼稚園のころと違い、小学生はある程度自分で考えて行動をする必要があるのかもしれません。
「授業が分からない」に、親はどう対応したのか
親として以下のようなフォロ-をしました。特に意識したのは、授業が分からなくても焦らず、安心できるようにサポ-トすることです。授業が「分からない=ダメな子」ではなく、あとから復習や塾などで取り戻せばいいのです。
1. 話をじっくり聞き、心のケアを
- 「どの教科が分からないの?」「いつからそう思ったの?」など、子どもの気持ちを丁寧に聞いた。
- 授業が分からなくても焦らなくていいことを、繰り返し伝えた。
- 「分からない=ダメな子」と誤解させないように接した。
- 親が焦ると子どもにも不安が伝わるため、安心できる雰囲気づくりを心掛けた。
2. 無理に詰め込まない・自信をつけさせる
- 「できたね!」「昨日より分かってるね」と小さな成功を積み重ねる。
- 比較ではなく、本人のペースで成長を見守る。
3.一緒に授業の内容を予習、復習。
- 学校の宿題に付き合いながら理解が不十分なところをフォロー。
4.学校以外の学びも活用!
- 家庭教師・個別指導塾の検討。
- 通信教育・学習アプリ・学童保育の学習時間を活用。
塾などの利用も検討しましたが、わが家では1年生から続けている【進研ゼミ小学講座】を活用していました。子どもと一緒に予習・復習に取り組みました。進研ゼミの教材は、学校の教科書の内容に沿っているので、予習、復習に役立ちました。
年度末には先生が一番成長していた???
1月に行われた2年生最後の授業参観。1年間の児童たちの成長を見ることができる機会でもあると思います。しかし、一番成長が見られたのは、新任(担任)の先生でした!
4月の授業参観に比べ格段に授業の進行がスムーズになっていたのです。タブレットのタイマー機能を活用して、授業は時間通りに効率よく進行。補足資料をプロジェクターで黒板に投影するなど、授業の質が格段に向上していました。
まさに”若さ”は伸びしろ。この1年で子ども達と共に大きく成長していたのです。
トラブルがあった際の対応
小学生の子供たちは、まだまだ未熟で学校生活でトラブルが起こることもあると思います。まだ経験の浅い新任の先生ではうまく解決に導けないこともあるでしょう。
もし、新任の先生だけでは解決が難しいと感じたら、学年主任や教務主任の先生など他の先生に相談してみましょう。学校でのトラブルは、担任だけでなく学校全体で考えるべきことです。どうしても改善されない場合は、教育委員会など外部に相談することも視野に入れましょう。
新任の先生には経験が少ないため、至らない点もあるかと思いますが、あたたかく見守る気持ちも持って接していきたいですね。そもそも、大学卒業したての新人にいきなり担任を任せているのは学校であり、国の教育制度。新任の先生個人だけを責めても、問題の根本的な解決にはつながらないことの方が多いでしょう。

担任が新任の先生でも大丈夫?娘のリアルな感想を紹介!
ベテランと新任の先生に関する娘の生の声をまとめてみました。あくまで娘の主観なので、参考までに。
| ベテランの先生 | 新任の先生 | |
| 良いところ | ・授業が分かりやすい ・授業中に席を立つ子がいない ・授業中断が少ない | ・一緒に体を動かして遊んでくれる(鬼ごっこなど) ・授業でのタブレットの活用(視覚的に分かりやすいことがある) |
| いまいちなころ | ・授業でタブレットをあまり使用しない ・体を使った遊びは少ない(鬼ごっこなど) | ・授業中に席を立つ子がいる ・授業中に騒がしくなることがある ・授業がたびたび中断 |
まとめ:担任が新任でも大丈夫!子どもはしっかり成長します
新学期に「担任が新任の先生」と聞いたとき、多くの保護者が不安を感じるのではないでしょうか。私も当初は「うまくやっていけるのかな…」と心配でした。でも、1年間を通じてわかったのは、新任の先生だからこそできる関わり方があるということ。新任=不安要素と思いがちですが、決してマイナスばかりではなく、子どもと一緒に成長していける存在でもあると思います。
もちろん、ベテランの先生には安心感や指導力といった強みがあり、それぞれに良さがあります。だからこそ、さまざまなタイプの先生と出会うことが、子どもたちの学びにもつながると実感しました。この先も授業が分かりにくい先生にあたることもあるかもしれません。それでも、子ども自身が考えたり工夫したりすることが、成長につながります。そして、親が状況を冷静に見守り、必要に応じてサポートをする姿勢が大切だと感じました。子どもが感じている違和感や戸惑いにも、しっかり耳を傾けていきたいですね。
以上、参考になるとうれしいです。
注)新任の先生にも個人差があると思いますので、本記事はあくまで参考としてください。
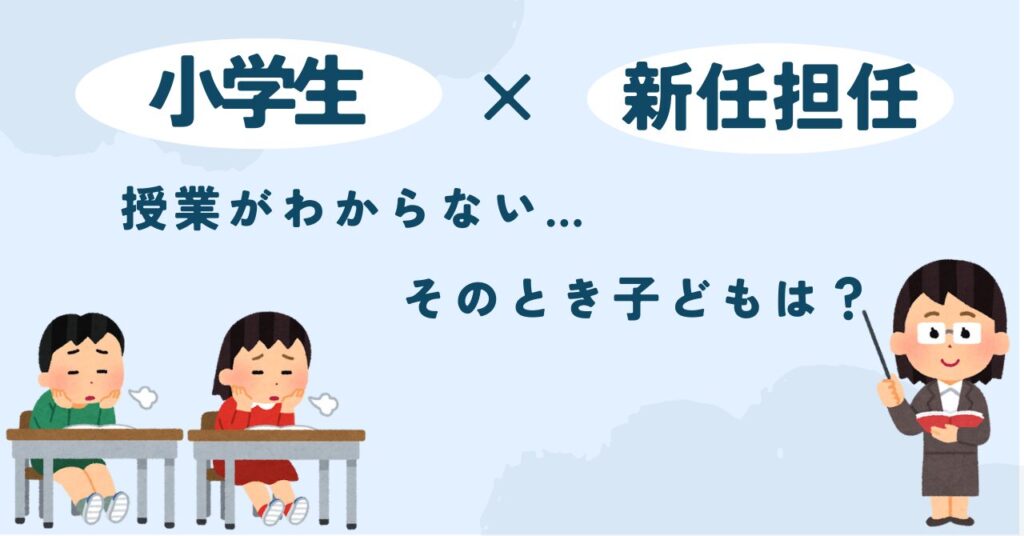

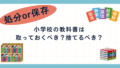
コメント